第6章 闇から光へ、ふたたび──バロック・近代・現代を歩く(B1・1F・2F)
■ 再び屋内へ──時代はゆっくりと「近代」へ変わり始める
昼食を終え、
青空の広がる展示から、
再び“絵画の中の光”へと戻る。
次に向かうのは、ルネサンスの整った光を越え、
人の心の揺らぎへと踏み込んでいく近代の層。
モネの庭をあとにして階段を上ると、
空気がわずかに重たくなるのを感じた。
ここから先は、絵画が「光と闇」で
人間の内奥まで描こうとした時代――
バロックから近代へと至る深い層だ。
■ ゴヤ《黒い絵》──闇の底に置かれた一つの灯り

最初の部屋に入った瞬間、世界がぐっと暗く沈んだ。
中央にぽつんと置かれたテーブルと椅子、その上だけに当てられたひとつの照明。
まるで「闇そのものについて語り合うための席」のようだ。
壁を覆うのはゴヤ晩年の《黒い絵》。
狂気、絶望、静かな諦め――
人間の心の底の底を、容赦なく突きつけてくる。
しかしその闇の中で、照明は確かに作品へ寄り添っている。
「見捨てない光」だけが、この部屋をかろうじて支えていた。
■ ゴッホ《ひまわり》──絶望の裏側で燃える黄金の光

《黒い絵》の余韻を引きずったまま次の部屋へ向かうと、
突然、世界がまばゆい黄金色に変わった。
ゴッホ《ひまわり》7点が並ぶ展示室。
黄色は一枚ごとに違い、その差が部屋全体の光の層となって揺れている。
これはただの明るさではない。
絶望の底で、それでもなお絞り出した希望の色。
黄金の波に包まれていると、
「光は必ず戻る」という声が確かに聞こえてきた。
■ ドラクロワ《民衆を導く自由の女神》──戦場に掲げられた光

近代の展示へ入ると、空気が再び引き締まる。
戦場の煙を突き抜けて、ひときわ強い光が前方に立っていた。
ドラクロワ《民衆を導く自由の女神》。
旗と胸元を照らす強烈な明暗は、ただの記録画ではなく、
「光を掲げる行為そのもの」がテーマなのだと伝えてくる。
闇の中に火が点く瞬間――
その象徴が、この部屋の中央に立っている。
■ ミレー《落穂拾い》──静かな午後の光

戦場の光を抜けると、世界は一気に日常へと戻る。
ミレー《落穂拾い》。
農民たちの背中に落ちる午後の光は、強くも弱くもなく、
ただ“暮らしの重さ”をそっと包んでいる。
自由を叫ぶ光とはまったく違う、
生きることを淡々と支える光。
ここで鑑賞のテンポがふっと落ち着き、
深呼吸をひとつした。
■ ムンク《叫び》──揺らぎの色を描く
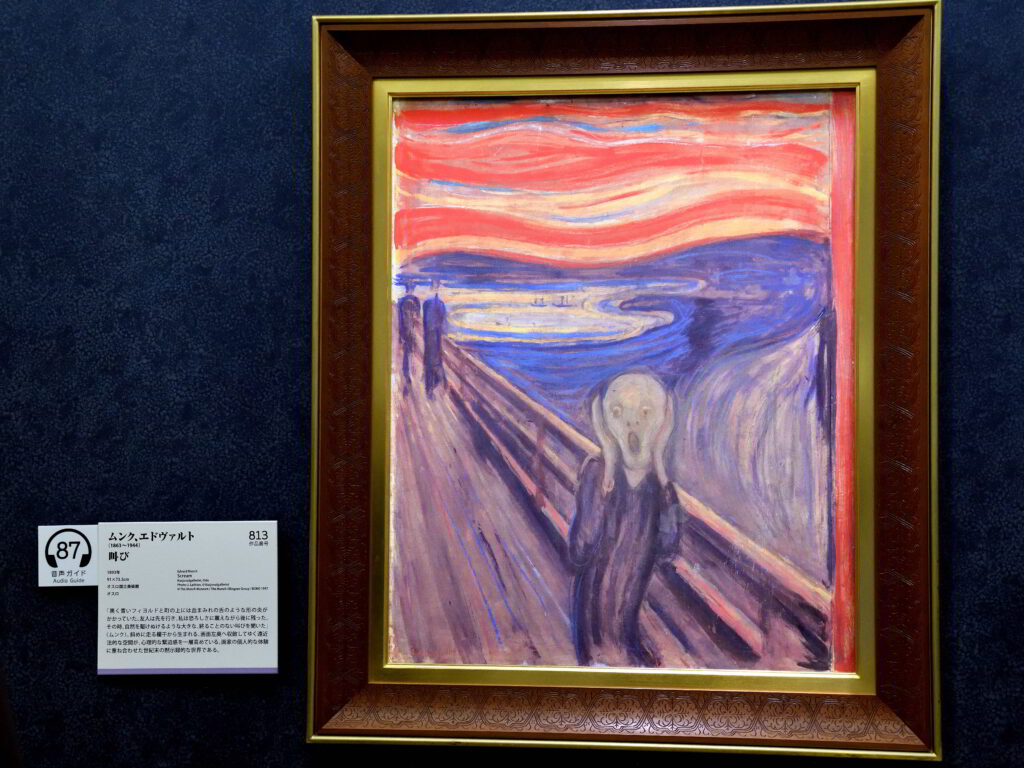
落穂拾いの静けさを抜けると、
空気が再びざわりと揺れた。
《叫び》の前に立つと、背景の赤と青の波が震えながら迫ってくる。
それは“光”でも“闇”でもない、
その中間にある不安の震動そのもの。
ムンクが人生で抱えた心の乱れが、
色彩となって観る者の胸の奥へ響いてくる。
■ ピカソ《ゲルニカ》──光が断ち切られた世界

次の展示は一気に世界観が変わる。
白と黒だけで描かれたピカソ《ゲルニカ》。
光はほとんど奪われ、
残っているのは鋭い電球の白だけ。
世界が崩れ落ちるその瞬間を、
光と闇の断絶で描いた作品。
さきほどまでの“色の揺らぎ”すら奪われた空間は、
ただ静かに息をひそめていた。
■ レンブラントの部屋──光が闇をつくる場所

展示の終盤、動線が少し曲がった先に、
ひっそりと“原点”の部屋が現れた。
レンブラントの自画像が並ぶ小さな展示室。
陰影の深さはゴヤとはまったく違う。
光があって初めて暗さが生まれる――
その当たり前のことを、レンブラントは徹底して描いた。
人物の頬、手、眼差し。
わずかな光の角度だけで、感情が立ち上がる。
この部屋に来て初めて、
“光とは闇と共にある”という事実が
静かな説得力をもって胸に落ちた。
■ 静かな出口で、光と再会する
光をめぐる絵画の歴史をたどり終え、
出口に近づくと、外からの淡い明るさが足元を照らした。
暗さの中に寄り添う光。
叫びの中から立ち上がる光。
失われ、また戻ってくる光。
先ほどまでの展示室で見てきた多様な“光の姿”が、
この淡い自然光とどこか静かに響き合っているように思えた。
まだ日は高い。
けれど、その明るさの中にさえ、
物語の続きをそっと示すような揺らぎがあった。
次の章では、
現実の光が、この旅をどのように締めくくるのかを描くことになる。
第7章 瀬戸の夕景が、旅の最後に灯すもの — 与島SAにて
高速道路を北へ走りながら、
大塚国際美術館で見た光と闇の余韻だけが、
まだ胸の中で小さく揺れていた。
外の景色はゆっくりと夕暮れへ変わりつつあり、
高松を過ぎ、坂出へ近づくころには、
西の空にほんのわずかな赤みが残るだけになっていた。
「与島、寄っていこうか」
そう自然に声が出た。
今日の旅はまだ、静かに続いている気がした。
■ 橋の全景──沈んだ光の中に浮かぶ“影”の橋

展望台へ上がると、
瀬戸大橋は沈んだ陽の余光の中で、淡い影となって海に横たわっていた。
強い逆光ではない。
輪郭がくっきり浮かぶわけでもない。
ただ、
空に残った薄い赤みが、
橋の線と海の境界をそっとなぞるように照らしていた。
“光に照らされている橋”ではなく、
“光が退いた後にだけ現れる橋”だった。
今日追いかけてきたすべての光が、
一度静かに沈んでいくような、そんな時間だった。
■ 夕陽が橋を染める──色が消えていく時間の中で

陽はすでに沈み、
空は赤から藤色へとゆっくり変わりはじめていた。
その残光が、橋を淡く縁取っていた。
強烈な光ではなく、
光が退いていく最後の呼吸のような色。
思い返せば3日間、
光の中を歩いてきた。
明石海峡の白い輝き。
淡路の岬を染めた夕陽。
うずしおの渦を照らした複雑な反射。
淡路人形座の舞台に宿る炎のような照明。
鳴門公園で追い求めた、あの束の間の夕焼け。
そして、美術館で触れた光と闇の深い歴史。
この旅で見たすべての光が、この薄明の中で再び静かに立ち上がる。
■ 海が吸い込む色──もう戻らない一日の名残り

海はほとんど光を失いながらも、
わずかな金色の名残を抱えて揺れていた。
青と紫の境界が、
波の動きに合わせてゆっくり変化していく。
目の前にあるのは、
“光がある景色”ではなく、
“光が失われることで生まれる景色”。
その静けさは、
観光地のざわめきも、車の音も、
すべてを遠くへ押しやるほど深かった。
このわずかな時間だけは、
世界が光の名残だけで形を保っているように思えた。
■ 色の消失と再生──夜がそっと島影を包みはじめる

空に残っていた赤みが静かに薄れると、
島の稜線へ淡い黄金の光がそっと降りていった。
海面には、その光が細い筋となって揺れながら伸びている。
橋よりもむしろ、
対岸の島と海が“最後の光”を受け止めているようだった。
黄金でも橙でも藤色でもない、
そのどれでも始まってどれでも終わらない、
“色がほどけていく時間”。
光が消えていくのではなく、
次の光へそっと引き継がれていくような、
やわらかで確かな移ろいだった。
大塚国際美術館で見た光――
闇の底に置かれたゴヤの灯り、
希望を燃やすゴッホの黄色、
静寂をつくるミレーの午後、
波打つムンクの痛み、
断絶を走るピカソの白、
そしてレンブラントの陰影。
そのすべてが、
この“色の消失”のシーンと静かに呼応している気がした。
まるで旅そのものが、
与島の夕景にそっと“最後の一筆”を描き加えたかのようだった。
■ 岡山へ──光の記憶を連れて帰る
完全な夜が訪れ、
橋の灯りがひとつ、またひとつと海に落ちていく。
展望台を降り、
ハンドルを握ると、胸の奥にはまだ
“さっきまで確かにそこにあった光”が
ゆっくりと温度を残していた。
言葉にするほどでもない、
ただ静かに満ちていく余韻。
瀬戸大橋を渡り切れば、もう岡山だ。
暗い車窓を流れる光の粒のなかで、
旅がそっと日常へと戻っていくのを感じながら、
車は静かに家路をたどっていった。
— 完 —
文:caritabito